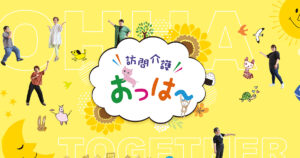奈良県では年に1度、「強度行動障害支援者養成研修」が開催されています。
私はこの研修に講師として関わらせていただき、今年で3年目になります。今日は全4日間の最終日です!
この研修は、国が実施するオンライン研修(Zoom)を受講した後、各都道府県で「伝達研修」として行うもので、私は奈良県でその一端を担わせていただいています。
おととしからは国の方針として、福祉関係者だけでなく、特別支援学校や特別支援学級など教育分野の方々にも参加が促されるようになりました。
強度行動障害とは
1989年の「強度行動障害児(者)の行動改善および処遇のあり方に関する研究」では、次のように定義されています。
① 強度行動障害児(者)とは、直接的他害(噛みつき・頭突きなど)や、間接的他害(睡眠の乱れ・こだわり・多動・飛び出し・器物損壊など)や自傷行為などが、通常考えられない頻度と形式で出現し、その療育環境では著しく処遇が困難なものをいう。
② 医学的には自閉症児(者)、精神薄弱児(者)、精神病児(者)などが含まれるが、必ずしも医学的診断により定義される群ではなく、総合的な療育の必要性を背景として成立した概念である。
奈良県研修の特徴と目的
この研修では、強度行動障害のある方々を支援するための基礎的知識と実践的スキルを学びます。
特に奈良県の実施する研修は、
- 入所施設
- 日中活動(生活介護・就労)
- グループホーム
- 相談支援
などの支援現場に特化しており、実践に即した内容が中心です。
また、類似する研修に「行動援護支援者養成研修」があります。こちらは外出支援などを行う際に必要な資格取得研修です。どちらも修了すれば同じ資格となりますが、施設系支援を深めたいのか、外出支援系を極めたいのかによって、選ぶ研修が異なります。
私がこの研修に関わる理由
私がこの奈良県研修に関わっているのは、
「強度行動障害のある方々が行く場所がない」
「地域で暮らしづらい」
という現実を少しでも減らしたいからです。
在宅での生活を続けるためには、専門的な知識と実践力を持った支援者の存在が欠かせません。
だからこそ、研修を通じて一人でも多くの支援者に「理解」と「技術」を届けたいと思っています。
もちろん、研修を受講することで事業所には加算がつくという現実的なメリットもあります。
けれども私が大切にしているのは、“加算のためではなく、専門性を持った支援者を増やすこと”です。
それが結果的に、強度行動障害のある方々が安心して暮らせる奈良県づくりにつながると信じています。
おわりに
今年も約80名の受講生が参加されています。
この中から、1社でも多く、強度行動障害のある利用者さんを受け入れ、専門性をもって支援してくださる事業所が増えていくことを心から願っています。
地域で共に生きるために。
“その人らしい暮らし”を支える仲間が奈良にもっと広がっていきますように。